
「退職代行サービス」は世の中に定着しつつあり、会社を退職する際に利用しようと考えている人も多いと思います。
しかし退職代行には「簡単に会社を退職できる」というメリットの一方でデメリットもあり、退職代行のデメリットを理解しないままサービスを利用して、退職トラブルに巻き込まれるケースも見られます。
ということでこのページでは、
- 退職代行サービスのデメリットは何?
- 具体的なデメリットの解決方法
- 退職代行で考えられるリスクやトラブル
について、詳しく説明していきます。
最後には、失敗しないための「退職代行の選ぶポイント」もご紹介しますので、ぜひご一読ください。
1. はじめに
退職代行サービスのデメリットについて触れる前に、そもそも退職代行とはどんなサービスなのか、おさらいしておきましょう。
1-1. 退職代行サービスとは

退職代行とは、会社を辞めたい人に代わって会社へ退職の意思表示をしてくれるサービスです。
退職代行サービスを利用することで、会社を辞めたいと思っているのに引き止めにあって会社を退職できなかったり、退職したいと言い出せない人の代わりに会社へ退職の意思表示をしてくれます。
「退職するだけなのに人に頼むなんて…」と思われる方も多いかもしれません。たしかに退職する自由は労働者に求められた権利で、一般的な会社であれば断られることはないでしょう。しかしその一方で、労務上の問題を抱えた“ブラック企業”も数多く存在し、仕事で心を病んでいる人も大勢います。
どんな時に退職代行が必要となっているのか、具体的な事例を見てみましょう。
事例1)退職が言い出しにくい・言い出せないケース
私も経験がありますが、会社へ退職の意向を伝えるのは、簡単のように見えて難しいものです。
今とは環境を変えたいと思っていても、良い職場、ブラックな職場を問わず、会社へ「退職したい」と言い出せず、ズルズルと数か月・数年と時間だけが経っていく…といった経験をした人も多いでしょう。
そういう時に第三者である退職代行を利用するのが最も多いケースです。
事例2)上司のパワハラなどが横行しているケース
上司が部下に対して高圧的に接する“パワハラ”気質の会社はまだまだ多く存在していて、そういった場合、上司への恐怖心から本当は退職したいのに言い出せないことがあります。
さらにパワハラなどのハラスメントが継続することにより、心を病んで退職を会社に伝えるのが難しくなるケースも。こうなると会社にいること自体が苦痛になってきます。
そういった場合は退職代行で今の環境から抜け出すのが良いでしょう。
事例3)退職を承認してくれず先延ばしにされるケース
退職の意思を上司に伝えたが上司預かりになってしまった、後任に引き継ぎが完了するまで退職を先延ばしするよう説得された、退職時期を会社が指定してきて大幅に退職が遅れそう、といったケースです。
人手不足が目立つ中小企業を中心に最近よく耳にするケースで、実際、かなり強い退職の引き留めも増えてきているようです。
本来、退職は自分のタイミングでするべきなので、2〜3か月以上先延ばしにされるようなら退職代行を使ってみるのも良いでしょう。
事例4)退職申請後に嫌がらせをされるケース
退職願を会社に出した途端、上司や同僚から冷たい仕打ちを受けたり、退職までの期間で嫌がらせが続くケースもあります。
仕事や引き継ぎに必要なファイルにアクセスできなくしたり、仕事が振られなくなったり、逆に面倒な仕事を押し付けられたりするハラスメント的な環境に置かれて心身を病んでしまう人もいます。
「もう職場にいたくないな」と感じたら退職代行を使って前倒しで辞めたり、有休消化に入ったりすることも検討しましょう。
こういったケースのように「会社を辞めたいのに辞めれない…」そんな悩みに対応してくれるのが「退職代行サービス」です。
2. 退職代行サービスのデメリットと解決方法

では早速、本題に入っていきましょう。
結論から言うと、退職代行には7つのデメリットが考えられます。具体的なデメリットとあわせて、デメリットを解決する方法を順番に紹介していきます。
デメリット1:退職後に会社の人との関係が悪くなる
退職は、まず自分で直属の上司に退職の意思を申し出て了承を得た後、様々な引き継ぎを済ませて最後に各方面に退職の挨拶をする、というのが一般的流れです。
しかし退職代行サービスを使う場合、これらのプロセスを全部すっ飛ばし、退職代行会社からの「〇〇さんは御社を退職します」という連絡一つで、強引に退職することになります。
退職代行サービスを使えば、退職に伴う煩雑さを伴わないので非常にラクに退職できるのですが、その一方で会社の人から見るとどうしても「あいつは飛んだ(逃げた)」という印象を残してしまいがちです。
もちろん退職代行を使わざるを得ない事情を理解してくれる人もいるでしょうが、退職代行を利用した退職には賛否両論があり、否定的に捉える人も多いのが現状です。
そのため、退職代行を使うと退職後は関係が悪化する可能性が高く、会社の人とは縁を切る覚悟を持っておいた方がよいでしょう。
【解決方法】関係を続けたい人には事前に根回ししておく
会社の中にもしどうしても退職後も関係を続けたい人がいるなら、事前に自身が退職を考えている状況を伝えておいたり、場合によっては退職代行を使って退職することを伝えておくとよいでしょう。
ただし退職代行を使って退職することを事前に会社の人に伝えてしまうと、会社や上司に漏れてしまうリスクは頭に入れておくべきです。話をするのであれば、信頼できる相手に絞りましょう。
デメリット2:会社から本人や家族・実家に連絡が行くことがある
退職代行を使って退職すると、会社から「どういうことなのか?」「本当に退職するのか?」「退職するのを止めて欲しい」などの連絡がくることがあります。
どの退職代行会社も「会社から連絡がいくことはありません」と謳っていますが、会社から本人や家族・実家へ連絡がいかないように、しっかりと伝えて念を押すことをしない退職代行会社も存在します。
そういった業者に当たってしまうと、家族や実家に会社から連絡が行き、予定外の大騒ぎになってしまうこともあります。
【解決方法】弁護士または労働組合運営の代行会社へ依頼する
退職代行会社には「弁護士運営」「労働組合運営」「一般法人運営」の3つの種類が存在します。
その中で、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスは法的に会社側との交渉が認められていますが、一般法人運営の退職代行サービスは会社との退職交渉が法的には認められていません(交渉すると違法)。
つまり、弁護士や労働組合の退職代行は「本人や家族・実家へ連絡しないよう会社へ働きかける」ことができますが、一般法人の退職代行は「連絡しないで欲しいという本人の希望を伝える」ことだけしかできず会社側の対応に任せるしかありません。
弁護士や労働組合でも100%、本人や家族・実家への連絡を止めることはできませんが、抑止力としては一般法人に比べて数段上となります。会社からの連絡を防ぐには、弁護士または労働組合が運営する退職代行会社を利用すると良いでしょう。
デメリット3:同じ業界に転職しづらい可能性も
狭い業界だと、同業他社の人事情報は筒抜けになってしまうもの。そのため退職代行を使って退職したことも、同業他社へすぐに知られてしまう可能性があります。
狭い業界内で転職しようと考えている人は、退職代行を使う際に十分注意するようにしましょう。
【解決方法】覚悟を決めるか、同業や隣接業界での転職を諦めることも考えよう
同業もしくは隣接業界での転職を考えていて、その業界が狭い場合、退職代行を使った退職には相当な覚悟が必要です。
転職活動が厳しくなることはもちろん、転職後も「あの人は〇〇社を飛んだ(辞めた)人だ」と後ろ指を指されることもあるかもしれません。
こんな場合は、覚悟を決めるか、同業・隣接業界での転職を諦めてまったく別の業界で働くことも視野に入れてみましょう。
デメリット4:退職代行費用がかかる
当たり前の話ですが、退職代行会社に依頼すると料金がかかります。
退職代行会社は大きく「一般法人の運営」「労働組合の運営」「弁護士の運営」の3つに分かれますが、料金の相場は一般法人で1~2.5万円、労働組合は2.2~3万円、弁護士は5~10万円程度となっています。
退職代行を使うことで退職に伴うあれこれの煩雑さから解放されるのは大きなメリットですが、どうしても2〜3万円程度のお金がかかってしまうのはデメリットといえるでしょう。
【解決方法】料金の安い業者に依頼する?
料金を安く済ませたい場合、一般法人が運営する退職代行会社という選択になります。
後程詳しく触れますが、一般法人の業者は、労働組合法に基づき団体交渉ができる労働組合や、弁護士法に基づき一切の法律事務ができる弁護士に比べると、できることがかなり限られ、退職に失敗するケースもあります。
退職に失敗する可能性を理解した上で安さを選ぶかは難しい判断ですが、もし今現在はお金がないけど来月は大丈夫ということであれば、クレジットカードで支払いができる労働組合運営の退職代行会社もありますので、検討してみると良いでしょう。
デメリット5:有休消化・未払い給与や残業代の交渉・請求ができない場合も
退職に伴い有給休暇が残っている場合や、未払い給与や残業代がある場合はこれらの取得・請求の交渉をしたいですよね。
しかし、取得・請求ができる退職代行会社は労働組合と弁護士のみで、一般法人の代行会社はできません。
これは法律の縛りがあるためで、一般法人の運営業者が有給消化や未払い給与・残業代請求の交渉をしたとしても、会社側から「違法な行為」として無効を主張され、退職を含めてすべてを覆される可能性大です。
一般法人・労働組合・弁護士によってできることは以下の表にまとめてみました。
| 業務内容 | 一般法人 | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 退職に関する調整・交渉 | × | ◎ | ◎ |
| 有休消化申請 | × | ◎ | ◎ |
| 離職票などの請求 | × | ◎ | ◎ |
| 裁判になった時の対応 | × | × | ◎ |
| 料金相場 | 1〜2.5万円 | 2.2〜3万円 | 5〜10万円 |
【解決方法】労働組合か弁護士が運営する退職代行会社に依頼する
退職代行は退職の意思を会社に伝えて終わりではありません。
退職代行を実行する上で、退職日・有休の取り扱い・未払い賃金の支給・離職票や源泉徴収票の請求・会社からの貸与品の返却といった調整・交渉が必ず発生するので、必ず労働組合か弁護士が運営する退職代行会社に依頼しましょう。
さらに未払いの残業代を会社へ認めさせて請求したい場合や、ブラック企業で退職が揉めそう場合は、料金が高くなりますが、弁護士運営の退職代行サービスを利用するようにしましょう。
デメリット6:ボーナス(賞与)がもらえない場合も
退職代行を利用した退職の場合、ボーナス(賞与)がもらえない場合があります。
働いた分の給与の支給は労働基準法で定められているので、必ずもらうことができますが、ボーナスの支給は法律の定め(つまり支払い義務)がなく、それぞれの会社の就業規則で定められているに過ぎません。
そのため「ボーナスの支給対象期間は勤務していたのでボーナスはもらえるはず」と思っても、就業規則によっては支給されないことがあるので要注意です。
【解決方法】ボーナスが支給されてから退職する
確実にボーナスを受け取るには、ボーナスが支給されてから退職するのがおすすめです。
ただし露骨にボーナス支給してすぐ(当日や翌日)に退職するのは、会社側の態度を硬化させていらぬ争いを生む可能性があります。ボーナス支給後すぐの退職は避けて一週間程度は間を空けるのが良いでしょう。
ボーナス支給前に退職する場合は、就業規則の中の賞与に関する項目、特に「支給不可・減額の条件」について確認し、就業規則の内容を含めて労働組合か弁護士が運営する退職代行会社に事前に相談するのがベストです。
デメリット7:有期雇用契約の社員や公務員は退職代行を利用できない場合も
「有期雇用」とは、契約社員など期間を定めて行われる雇用のこと。一方「無期雇用」という言葉もありますが、正社員として働いている方が該当します。
無期雇用契約(正社員)は法律で「退職の申し出から自動的に2週間後に退職できる」と定められていて、正社員の多くは退職代行を利用した退職に失敗することはありません。
しかし有期雇用契約の場合、契約開始から1年以上経過していなければ「やむを得ない事情」がない限り退職できないとされています。
「やむを得ない事情」とは、本人の病気や出産・育児、家族の介護が該当しますが、医師の診断書や公的機関の証明書などが必要で、診断書や証明書が用意できない場合は、会社に法律を盾にされると退職交渉がスムーズに進まないこともありえます。
また、公務員の退職は原則として任免権者(大臣や知事・市区町村長など)が法律に基づいて行うことになっていて、民間のように退職代行を利用して簡単に退職することはできないので、注意が必要です。
【解決方法】経験豊富な弁護士が運営する退職代行会社に依頼する!
有期雇用契約の社員や公務員は退職交渉が難しいのですが、退職できないというわけではありません。
有期雇用契約の社員や公務員の方で退職代行を使って仕事を辞めたい場合は、一般法人や労働組合では対応ができないことが多いため、弁護士の退職代行サービスを利用することになります。
3. デメリット以外に考えられる退職代行のリスクやトラブルは?
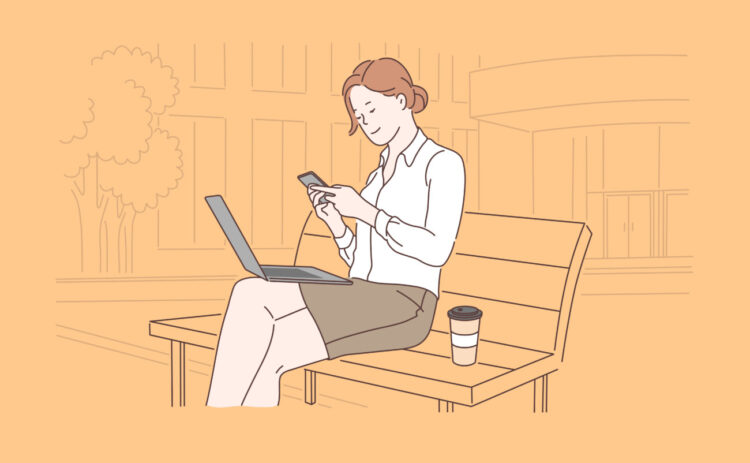
ここまで退職代行の7つのデメリットをご紹介しましたが、次にデメリット以外に考えられる退職代行のリスクやトラブルも確認しておきましょう。
3-1. 悪質な退職代行会社に当たる可能性がある
退職代行サービスは、資格や許可の必要がなく誰でも始めることができるため、中には悪質な業者も存在します。
悪質な業者の中には「料金を支払ったら音信不通になった」「退職に失敗した」といったケースも報告されています。
特に一般法人が運営する退職代行会社の場合は、会社がしっかり存在しているのか、本当に退職実績があるのかを確認する必要があります。
労働組合の場合も「自称労働組合」と呼ばれる、見た目は労働組合でも運営者は一般法人のケースもあるため、しっかり見極めるようにしましょう。
3-2. 懲戒解雇や損害賠償請求に発展する可能性がある
通常の正社員(無期雇用契約)の場合、退職は退職代行の利用に関わらず合法的にできます。
しかし会社が常識の通じないブラック企業の場合や、法律的に自由に退職できない有期雇用契約や公務員に該当する場合、退職が認められず懲戒解雇にされたり、最悪の場合は損害賠償請求に発展するケースもあります。
最終的に裁判になっても、余程のことがなければ会社側の訴えが認められることはありませんが、長期間にわたって面倒なトラブルに巻き込まれるのは、費用も掛かり精神的にも追い詰められます。
ブラック企業に勤めていたり、有期雇用契約や公務員に該当する場合は、弁護士運営の退職代行会社を使うようにしましょう。
4. 退職代行選びで知っておきたい8つのポイント

ここまで退職代行のデメリットやリスク・トラブルとあわせてその解決方法について触れてきましたが、一番重要なのは「退職代行の業者選び」です。
次に退職代行選びで知っておきたい8つのポイントについてご紹介しましょう。
既に触れたことと内容がかぶる部分もありますが、失敗しない為に大切なことなのでしっかりチェックしてくださいね。
4-1. 一般法人運営の業者は選ばない!
退職代行を実行する際、代行業者が会社へ連絡して退職日の決定や退職手続きの進め方、返却物・送付物の確認などの退職交渉を行います。
本人の代わりに会社側と退職交渉をすることになるわけですが、法的に認められない者が本人の代わりに交渉してしまうと「違法行為」となり処罰の対象となります。
具体的には、運営者が弁護士・労働組合のものは本人の代わりに会社側と退職交渉する法的根拠を持っていますが、一般法人が運営する退職代行は会社側との退職交渉はできません。
上の表にある通り、一般法人が運営する退職代行でできることは「◯◯さんが会社を辞めたいと言っています」ということを伝えることだけで、退職に関する交渉事はすべて出来ません。料金が安いからといって利用しないようにしましょう。
4-2. 退職代行選びは「運営者」を必ずチェック!
ここまで「退職代行は運営母体によって3つに分かれていて、弁護士もしくは労働組合運営の退職代行サービスを利用する」ことに触れましたが、この時にチェックするのが代行業者の「運営者」です。
代行業者のホームページには通常「運営者情報」が記載されているはずです(運営者情報が記載されていない業者は論外!)。そのページを見れば、運営者が弁護士・労働組合・一般法人のどれなのかがわかります。運営者が株式会社や合同会社の場合は、一般法人運営の退職代行なので利用しないのが良いでしょう。
ただし最近は、運営者が労働組合になっていても実際は一般法人が運営している“自称労働組合”も増えてきました。この“自称労働組合”の見分け方については次の項目でお知らせします。
4-3. さらに“自称労働組合”もチェック!
労働組合は比較的簡単に設立することができるため、労働組合を使って一般法人が退職代行を運営するケースが最近増えてきています。
本来、労働組合は会社経営からは独立しなければならないと法律で定められているため、一般法人とセットとなった“労働組合”は労働組合の要件を満たしていません。そのため「一般法人が運営する退職代行」の分類となり、違法性が高い代行業者といえます。
こういった“自称労働組合”運営の退職代行を見極める方法ですが「料金の振込先銀行口座を聞く」のが一番簡単です。
振込先銀行口座を聞いてみて口座名義が労働組合名ではなく一般法人名の場合は、ほぼ100% “自称労働組合”運営の退職代行と見てよいので、依頼は避けるようにしましょう。
【参考】退職代行会社の分類
参考までに主要な退職代行会社について弁護士・労働組合・一般法人に分類しておきます。「一般法人=悪質な業者」ではありませんが、退職代行で会社と交渉する上での法的根拠を持たない業者ですので、理由がない限りあえて選ぶ必要はないでしょう。
弁護士法人みやび・弁護士法人ガイア・フォーゲル綜合法律事務所 など
退職代行 退職サポート・退職代行ガーディアン・退職代行ニチロー など
退職代行モームリ・退職代行 OITOMA・退職代行トリケシ・退職代行リーガルジャパン・退職代行 Jobs など
この中で「退職代行 OITOMA」「退職代行トリケシ」「退職代行リーガルジャパン」「退職代行 Jobs」については「労働組合運営」を謳っていますが、いずれも運営会社が株式会社のため労働組合運営とは認められず、一般法人運営の退職代行へ分類しています。
チェックポイント
労働組合は比較的簡単に設立できますが、労働組合と認められる為には運営の高い独立性が必要です。運営会社が一般法人の場合、労働組合とは認められません。
4-4.「弁護士監修」「労働組合提携」の言葉にだまされるな!
退職代行のサイトを見ていると「一般法人運営の退職代行」の多くで「弁護士監修」「労働組合提携」という文字が踊っています。
一見すると、弁護士や労働組合が運営協力をしているようなニュアンスですが、実は「弁護士監修」「労働組合提携」には何の意味もありません。運営上で弁護士や労働組合が責任を持ってくれるわけではなく、弁護士や労働組合の運営としてみなせる訳でもありません。
「弁護士監修」「労働組合提携」と書かれていても、扱いは「一般法人運営の退職代行」のままで、違法性の高いことには変わりはないので注意しましょう。
4-5. 退職代行は退職率100%が当たり前!
同じく退職代行のサイトで良くみる文言に「退職率100%継続中」というものがあります。
ただ、これはある意味当たり前で、そもそも我が国で働く人には退職する自由が法律で保障されています。一部の契約社員や公務員などを除けば、退職の意思表示を会社にして一定期間が経過すれば自動的に退職が成立します。
必ず退職できる人のみを対象として退職代行を実行するのであれば「退職率100%」は当たり前といえます。
ちなみに一般法人運営の退職代行については撃退されることもあり、一定度の割合で退職代行が失敗していますが、失敗して返金処理をした場合は退職率のカウントから除外している業者もあるようです。
いずれにしても「退職率100%」は退職代行選びの参考にしない方がいいでしょう。
4-6. アフィリエイト広告を使っている代行業者は要注意!?
退職代行を利用する際にネットで情報を得ようと思う方は多いでしょう。
ただその一方で、退職代行業者の評判を検索したら良い内容だったので依頼してみたら最悪だった、という話も割とよく聞きます。
ネット上の情報で注意したいのは「アフィリエイト広告利用の有無」。
アフィリエイト広告とは、ブロガーなどが書いた紹介記事経由で商品購入などの成果が発生した際に報酬が支払われる「成果報酬型のインターネット広告」のことですが、基本的に広告主(退職代行業者)に対してネガティブな内容の記事はほとんど見かけません。そのためネット検索して得られた情報が良い内容だけに偏ることになります。
また「ステマ(ステルスマーケティング)」と呼ばれますが、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを意図的に発信しているケースも多く見られます。
退職代行を選ぶのであれば、できればアフィリエイト広告を利用していない業者が望ましく、アフィリエイト広告を利用している業者についてはネット上の評判を割り引いて考えるようにしましょう。
さらに、弁護士については職務規定や倫理規定上、広告利用について一般業種よりも制限が大きく、基本的にアフィリエイト広告の利用はグレーゾーンに当たります。弁護士の退職代行を利用したい方はアフィリエイト広告を利用している業者を避けることをおすすめします。
4-7. 退職代行業者は適当すぎ?外注&引継ぎは当たり前?
このサイトを作るにあたり、実際にいくつか退職代行を利用してみましたが、業務的にかなりアバウトで適当だと感じることも多々ありました。
一番気になったのは「担当者が都度変わる」ということ。
退職代行を利用する場合、LINEでのやり取りが一般的ですが、最初の無料相談・申し込み・事前ヒアリング・退職代行実行の報告といった節目節目で担当者が変わるため、伝えたことが伝わっていないことが幾度もありました。細かい依頼をお願いしてもきちんと引き継がれるのか怪しい、といった印象です。
また、退職代行の実行業務を(勝手に)外部へ委託している業者もあり、個人情報などの取り扱いが杜撰と感じたことも。
退職は失敗できない重要なことですので、できれば専任の担当者が付いてくれる代行業者が良いでしょう。
4-8. 退職代行は退職できたら終わりではない!
退職代行サービスの業務は、退職届が会社に到着して退職手続きが完了し、退職者が必要とする離職票などの書類が手元に到着するまでです。
しかし実際に退職代行業者とやり取りをしていると、退職したい旨を会社に伝達した時点で自分たちの業務は終了!と考えているところがほとんど。
そういった意味ではアフターケアー・アフターフォローがしっかりしている退職代行を選ぶ必要があります。フォロー期間は最低でも退職代行の実行日から1か月、できれば2か月以上ある業者を選ぶのがおすすめです。
-

-
【2024年7月】退職代行サービスおすすめランキング!主要10社を利用者の立場で徹底比較
退職代行サービスをご存知ですか? 最近「退職代行」を使って会社を辞める人が増えていて、利用を検討している方も多いのではないでしょうか? でも、現時点で退職代行の業者は100社以上あり、どの代行業者を使 ...
続きを見る
5. 退職代行を使った会社の辞め方・流れ

最後に一般的な退職代行サービスの依頼から退職完了までの流れを紹介しましょう。
step
1退職代行に無料相談
まずは、弁護士もしくは労働組合が運営する退職代行会社に連絡して相談してみましょう。
しっかり体制が整っている業者は24時間対応可能だったり、LINE相談可能だったりするので、そういった業者を選ぶと良いでしょう。
なお、この時点では料金は発生しません。
step
2退職代行を依頼
無料相談をして納得したら料金を入金します。
銀行振込やコンビニ払いが一般的ですが、退職代行会社の中にはクレジットカード払いに対応しているところもあります。
step
3ヒアリング・打ち合わせ
退職代行は素早い対応が基本。料金の着金を確認したら、すぐに業者は退職に向けて動いてくれます。退職代行の実施日、会社の連絡先や上司の名前などを聞かれますので、すべて答えられるようにしておきましょう。
また委任状などの提出を求められた場合は対応するようにしてください。なお、書類の提出についてはLINEやメール経由で行われますので、退職代行サービス側と直接会ってやり取りをする必要はありません。
step
4退職完了
あとは退職代行会社に丸投げで大丈夫。何もする必要はありません。業者が会社とやりとり・交渉をしてくれ、面倒な手間もなく最短即日で退職が完了します。
弁護士もしくは労働組合が運営する退職代行サービスであれば、会社に対して依頼者本人への直接接触はしないように要請してくれるので、会社から電話がかかってくることや、会社の人が自宅に訪ねてくるようなことは原則としてありません。
step
5貸与品の返却などの後処理を行う
退職代行の結果はすぐに退職代行会社から連絡があり、貸与品の返却方法などを案内されます。
会社に退職届を提出する必要がある場合もその指示がありますので、業者の案内や指示に従って後処理を進めてください。
あとは退職後に離職票や年金手帳などの「受け取るべきもの」を受け取ればすべての手続きは完了!
なお退職後にこれらが送られてこないといった問題が起きることがありますが、そのようなトラブルに備えて無料でアフターケアを行ってくれる退職代行会社に依頼するのがおすすめです。
6. まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は退職代行のデメリットと解決方法を中心に紹介しました。
何事にもメリット・デメリットはあります。デメリットを理解した上で退職代行サービスを活用するようにしましょう。
退職代行を上手く使えるかどうかの鍵は「代行会社選び」にかかっている、といっても過言ではありません。
退職代行は運営母体別に3つに分類でき、それぞれに特徴があります。自分の状況に合った代行会社を選べば、想定されるデメリットの多くは解決できます。
正しい情報で自分に合った退職代行サービスを見極めるようにしましょう。
【2024年7月】
退職代行 おすすめ業者3選!
最後に、退職代行を利用しようと考えている方へおすすめの退職代行会社をご紹介します。
| 会社名 |  退職代行 退職代行退職サポート |
 退職代行 退職代行ガーディアン |
 弁護士法人 弁護士法人みやび |
|---|---|---|---|
| 運営者 | 労働組合 | 労働組合 | 弁護士 |
| 即日退社 | ◎ | ◎ | ○ |
| 無料アフターケア | ◎ | ◎ | ◎ |
| 365日対応 | ◎ | △ | ◎ |
| LINE相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
| クレカ払い | ◎ | ◎ | × |
| 依頼手続きの手間 | ◎ 簡単 |
◎ 簡単 |
△ 面倒 |
| 料金(税込) | ◎ 22,000円 |
○ 24,800円 |
△ 55,000円+実費 |
| 評価 | 43点/50点中 |
34点/50点中 |
26点/50点中 |
| 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
退職代行サービスを使って会社を辞めたいなら、最新ランキング1位の「退職代行 退職サポート」がイチ押し!
安心できる労働組合運営の退職代行サービスで、料金も最安級の22,000円+退職後のサポート付きでコスパの良い退職代行業者です。
退職代行「退職サポート」